動物の難治性疾病に対する創薬研究 〜動物の免疫療法について〜
コラム 創薬研究

4. ウシの難治性感染症に対する創薬研究
牛伝染性リンパ腫(旧名:牛白血病)の発生原因は、牛伝染性リンパ腫ウイルス(Bovine leukemia virus: BLV)が原因となる地方病性がほとんどを占め、増加の一途をたどっています。原因ウイルスであるBLVは、牛のB細胞に感染し、細胞のゲノムにプロウイルスとして組み込まれ持続感染します。多くの感染牛は無症状ですが、約1~5%の感染牛では潜伏期間を経て感染細胞が腫瘍化し、リンパ腫を発症して、死に至ります。日本ではBLV感染が広がっており、2009〜2011年の全国調査では乳牛の40.9%、肉牛の28.7%がBLVに感染していると報告されています。牛伝染性リンパ腫は、家畜伝染病予防法で監視伝染病(家畜の重要疾病)に指定され、発症牛の届出が義務づけられています。2024年には4,423頭の発症が報告されており、1998年(99頭)と比べて44倍以上に増加しています。この発生頭数は、過去17年間にわたって、牛の監視伝染病37種のなかで最多となっています。現在のところBLVに対するワクチンや治療法はなく、農場の衛生管理やウイルス検査、感染牛の隔離・淘汰によって感染拡大防止が試みられています。しかし、日本国内ではリンパ腫発生増加に歯止めがかかっておらず、現状の対策だけでは十分ではないことが浮き彫りになってきています。一方で、市場を見ると、牛肉の価格は世界的な需要の増加と飼育費用の上昇により高騰しています。リンパ腫発症牛は食肉として売却できないだけでなく、それまでに費やした膨大な費用や時間が無駄になってしまうため、畜産業に大きな経済的損失をもたらしています。このため、感染拡大防止策に加えて、リンパ腫発生を未然に防ぐことが求められています。
北海道大学大学院獣医学研究院感染症学教室(旧伝染病学教室)は、1976年から牛伝染性リンパ腫の研究を行っております。年間数千頭のBLV感染症の迅速診断や感染防疫対策の指導・助言を行ってきました。その一方、臨床検体を用いた牛伝染性リンパ腫の病態発生機序および制御法に関する研究を行ってきました。BLV感染牛を病態別に比較解析した結果、血中ウイルス量が多いウシ(いわゆるハイリスク牛)は、発症リスクが高く水平感染源になりやすいことや垂直感染のリスクが高いことに加え、免疫能が低下し、他の感染症への感受性が高まっていることも明らかとなりました。さらに病態が進むに伴いPD-1やPD-L1などの免疫チェックポイント因子の発現が亢進し、その発現量はプロウイルス量などと有意な正の相関を示す一方、免疫抑制の指標であるIFN-γ発現量とは有意に負の相関を示し、PD-1/PD-L1経路などが牛伝染性リンパ腫における免疫抑制機序の一端であることが明らかとなりました。そこで、ウシ用の免疫チェックポイント阻害薬(PD-1およびPD-L1抗体)を作製し、牛伝染性リンパ腫ウイルス感染牛に対する臨床研究を行った結果、ともに抗体投与後に抗ウイルス免疫応答が活性化され、感染牛体内のウイルス量を減少させることに成功しました。
● 2017年4月27日:牛難治性疾病の制御に応用できる免疫チェックポイント阻害薬(抗 PD-L1 抗体)の開発にはじめて成功
(https://lab-inf.vetmed.hokudai.ac.jp/content/files/Research/2017.4.27_pr.pdf)
● 2017年6月7日:牛難治性疾病の制御に応用できる免疫チェックポイント阻害薬(抗 PD-1 抗体)を,抗 PD-L1 抗体薬に続き開発
(https://lab-inf.vetmed.hokudai.ac.jp/content/files/Research/2017.6.7_pr.pdf)
● Overcoming immune suppression to fight against bovine leukemia
(https://www.global.hokudai.ac.jp/blog/overcoming-immune-suppression-to-fight-against-bovine-leukemia/)
● 2019年8月7日:ウシの疾病に有効となる抗ウイルス効果の確認に成功~牛白血病などの新規制御法への応用に期待~
(https://www.hokudai.ac.jp/news/190807_pr2.pdf)
● The drug combination effective against bovine leukemia
(https://www.global.hokudai.ac.jp/blog/the-drug-combination-effective-against-bovine-leukemia/)
● 2019年12月25日:2019年農業技術10大ニュース選出「牛白血病の新たな制御方法、抗ウイルス効果の確認に成功-牛の難治性疾病に対する応用に期待-」
(https://www.hokudai.ac.jp/researchtimes/2019/12/-201910.html)
ヨーネ病はヨーネ菌の経口感染によるウシなどの反芻動物の慢性肉芽腫性腸炎で、難治性の慢性下痢と重度の削痩により衰弱死を引き起こします。ヨーネ病は家畜伝染病予防法により法定伝染病に指定されており、ウシの法定伝染病15種のうち唯一、日本国内で毎年発生が認められます。日本国内における2024年のヨーネ病届出数(牛)は1,198頭(速報値)で、北海道をはじめとして国内での発生が近年増加傾向にあります。 国内の農場でひとたびヨーネ病が発生すると、蔓延を防止するために、感染家畜の淘汰はもちろんのこと、決められた期間(年)、同居牛の検査義務、家畜の移動制限、畜舎の消毒義務などが課せられています。そのため、ヨーネ病は全国の酪農家にとって大きな経済的損失の原因となっており、様々な防疫対策が講じられているものの発生防止には至っていません。ヨーネ病の病態や免疫応答に関しては、未だに不明な点が多く、有効なワクチンや制御法がない極めて重要な家畜感染症の一つです。我々は、ヨーネ病の病態や免疫応答を詳細に解明し、より有効な対策法の樹立へ繋げるために研究を行ってきました。その結果、ヨーネ病の病態進行にもPD-1/PD-L1経路等を介した T 細胞の機能抑制(免疫疲弊化[仁山1] )が深く関与することが明らかとなり、これらの因子は、感染細胞からのプロスタグランジンE2によって誘導されていることを突き止めました。
さらに農研機構・動物衛生研究部門との共同研究で、免疫チェックポイント阻害薬(ウシ用PD-L1抗体)をヨーネ病罹患牛に投与する臨床研究を行った結果、抗体投与後に糞便に排出される菌量を減少させることに成功しました(Sajiki et al., J Vet Med Sci. 2021. 83(2):162-166.)。
● 2018年4月2日:ヨーネ病の病態発生メカニズムを解明 ~家畜法定伝染病ヨーネ病に対する制御法への応用に期待~
(https://www.hokudai.ac.jp/news/180402_pr.pdf)
● Unraveling the immunopathogenesis of Johne’s disease
(https://www.global.hokudai.ac.jp/blog/unraveling-the-immunopathogenesis-of-johnes-disease/)
マダニによって媒介されるAnaplasma marginaleはウシの赤血球に感染するリケッチアで、急性期に重度の貧血を引き起こし、感染牛の30%を死に至らしめる悪性感染症です。世界中で最も罹患率が高いマダニ媒介性疾患とされ、今なお世界中で甚大な被害を与え続けている感染症です。現在、日本での発生は認められておりませんが、法定伝染病に指定され、日本への侵入に注意が払われています。このアナプラズマ症でも抗原特異的CD4+ T細胞が急激に疲弊化することが知られていましたが、詳細な機序については不明でした。そこで米国ワシントン州立大学と共同で感染実験を行いT細胞疲弊化の分子機序を解析しました。その結果、この免疫疲弊には、PD-1やLymphocyte activation gene-3(LAG-3)といった免疫チェックポイント因子が関与していることが明らかとなりました(Okagawa et al., Infect Immun. 2016. 84(10):2779-90.)。一方でワクチン候補抗原とこれらの阻害抗体の併用により、疲弊化したCD4+ T細胞応答が再活性化されることも明らかとなり、現在新規制御法樹立として可能性を検証しています。
牛マイコプラズマ感染症は、肺炎や乳房炎、関節炎などを呈するウシの伝染性疾病で、特にMycoplasma bovisは病原性が高く、問題となっています。近年、本症の報告は世界的に増加傾向にあり、本症を発症すると、慢性に経過し極めて難治性に至ることから畜産業に甚大な経済的被害を与え続けています。牛マイコプラズマ症の病態形成にはマイコプラズマがもつ宿主免疫抑制作用の関与が示唆されますが、未だ解明には至っておりませんでした。そこで、酪農学園大学と共同でM. bovis感染牛の宿主免疫抑制の分子機序を解析した結果、M. bovis感染によって単球やマクロファージ上のPD-L1が誘導され、免疫を抑制していることが明らかとなりました。一方でPD-L1阻害抗体により、疲弊化した T細胞応答が再活性化されることも明らかとなりました(Goto et al., Immun. Inflamm. Dis. 2017. 5:355-363., Goto et al., Front Vet Sci. 2020. 7:12.)。さらに北海道立総合研究機構・畜産試験場との共同研究で、免疫チェックポイント阻害薬(ウシ用PD-L1抗体)をM. bovis感染牛に投与する臨床研究を行った結果、抗体投与後に肺中の菌量を減少させることに成功しました(Goto et al., Jpn. J. Vet. Res., 2020. 68(2):77-90.)。
<番外編>
オウシマダニは、主にウシに寄生する一宿主性のマダニで、亜熱帯及び熱帯地域を中心として世界的に分布しています。吸血被害だけでなくバベシア症や上記のアナプラズマ症など様々なマダニ媒介性感染症を伝播し、畜産の生産に深刻な被害を与えています。現在、殺ダニ剤を用いた制御法が主流であるものの、殺ダニ剤に抵抗を持ったオウシマダニの出現等により新規制御法の確立が強く求められています。
我々は、ブラジル連邦共和国のリオグランデドスール連邦大学及びリオデジャネイロ連邦大学と国際共同研究グループを形成し、免疫チェックポイント因子である PD-1 及び PD-L1に着目してオウシマダニ由来唾液が引き起こす免疫抑制との関連を解析しました。まず、試験管内(in vitro)においてウシの免疫細胞とオウシマダニ由来の唾液を培養したところ、PD-1 及び PD-L1 の発現が誘導されることを発見しました。さらに解析した結果、マダニの唾液が T 細胞の活性化及びサイトカインの産生を抑制すること、抗 PD-L1 抗体を用いて PD-1/PD-L1 経路を阻害するとマダニの唾液によるサイトカイン産生の抑制が観察されなくなることを明らかにしました。また、マダニ唾液を性状解析した結果、免疫チェックポイント因子の発現上昇に関与することが知られている生理活性物質プロスタグランジンE2が高濃度に含まれていることが明らかとなりました。オウシマダニの唾液の免疫学的解析により、マダニが PD-1/PD-L1 経路を介して宿主の免疫応答を抑制していることを証明した初めての研究であり、本研究で得られた知見は、マダニ媒介性病原体の伝播機序の解明やマダニに対する新規制御法への応用が期待されます。
● 2021年1月14日:マダニ唾液が免疫チェックポイント因子の発現を誘導 ~マダニ媒介性病原体の伝播機序の解明に期待~
(https://www.hokudai.ac.jp/news/pdf/210114_pr3.pdf)
おわりに
獣医免疫学を基盤とする研究は、ヒトやマウスの研究に比べかなりの後進研究で、研究者も少ないのが現状です。学会での発表数も他分野に比べ圧倒的に少ないです。動物疾病を対象とするワクチン・治療薬の開発研究も、決して活発であるとは言いがたく、多くの動物疾病は制御不能な状態です。動物を対象とする新規ワクチン・治療薬の開発は、ヒト以上に臨床応用時の生産コスト面を常に考慮せねばならなく、積極的な研究開発・応用が進んでおりません。その結果、未だ摘発・淘汰が多く、時には安楽死に頼ることもあります。しかし、淘汰一辺倒の制御法からの打開も必要であり、その為には免疫学を含めた様々な角度からのアプローチによる予防法や治療法の開発は必要です。世界中には種々な動物の疾病が存在し、今なお家畜生産性低下の一因や大切な伴侶動物との別れの原因となっています。それら疾病の原因は様々ですが、その原因に対する宿主の免疫応答もさらに様々です。E.ジェンナー氏の天然痘ワクチン開発の基礎に牛痘(正確には馬痘)が用いられたことは有名ですが、種々の動物疾病が今日のヒトのワクチン研究のモデルとなってきました。しかし、現状は既述の通りです。肝心の動物疾病もまた、今後さらなる病態発症機序の解明がなされ、新たな制御法確立への道が開かれることが望まれます。今回は限られたごく一部の動物疾病に対する創薬研究を紹介しました。北海道大学大学院獣医学研究院は、今後も生産者や飼い主様の願いに資する創薬研究を行って行きたいと思っております。また、動物の自然発生腫瘍や感染症はヒトの疾病と類似点が多く、ヒト疾病の治療モデルとして様々な臨床研究を行うことも可能であると考えられます。北海道大学大学院獣医学研究院では,今後も免疫療法の研究開発およびヒト用医薬品開発への橋渡し研究を目指した応用研究を展開していく予定です(図4)。
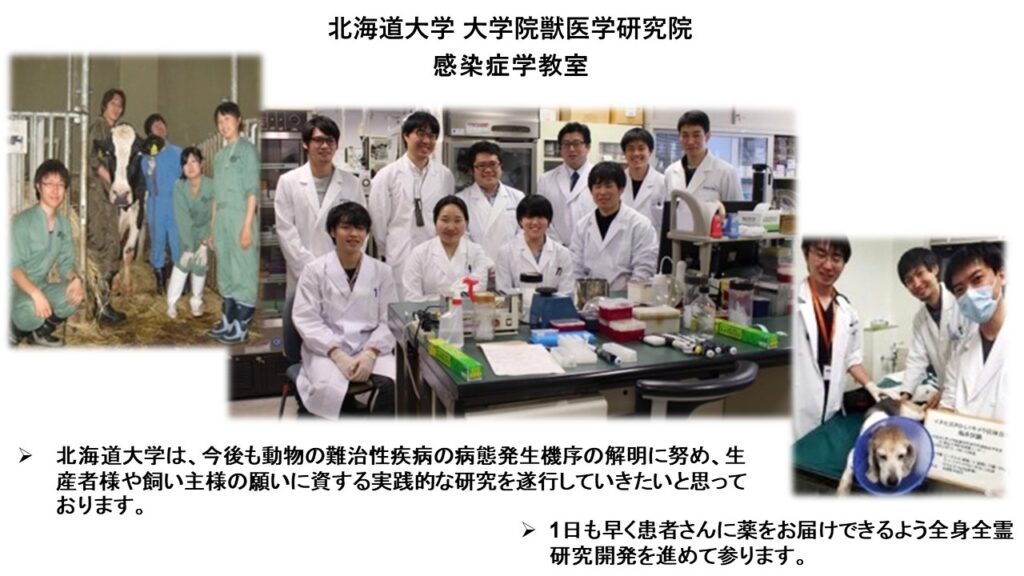
本研究成果の一部は、文部科学省科学研究費補助金、農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター革新的技術開発・緊急展開事業(うち地域戦略プロジェクト)および農林水産省委託プロジェクト研究・薬剤耐性問題に対応した家畜疾病防除技術の開発によって実施されたものであり、扶桑薬品工業株式会社、ノースラボ、細胞工学研究所、北海道農業共済組合、動物衛生研究所、国立感染症研究所、北海道立総合研究機構農業研究本部畜産試験場、東北大学、酪農学園大学、宮崎大学、北里大学、麻布大学などとの共同研究成果です。多くの共同研究者およびご協力頂きました皆様に深謝いたします。

 北海道大学大学院獣医学研究院 今内 覚
北海道大学大学院獣医学研究院 今内 覚 






