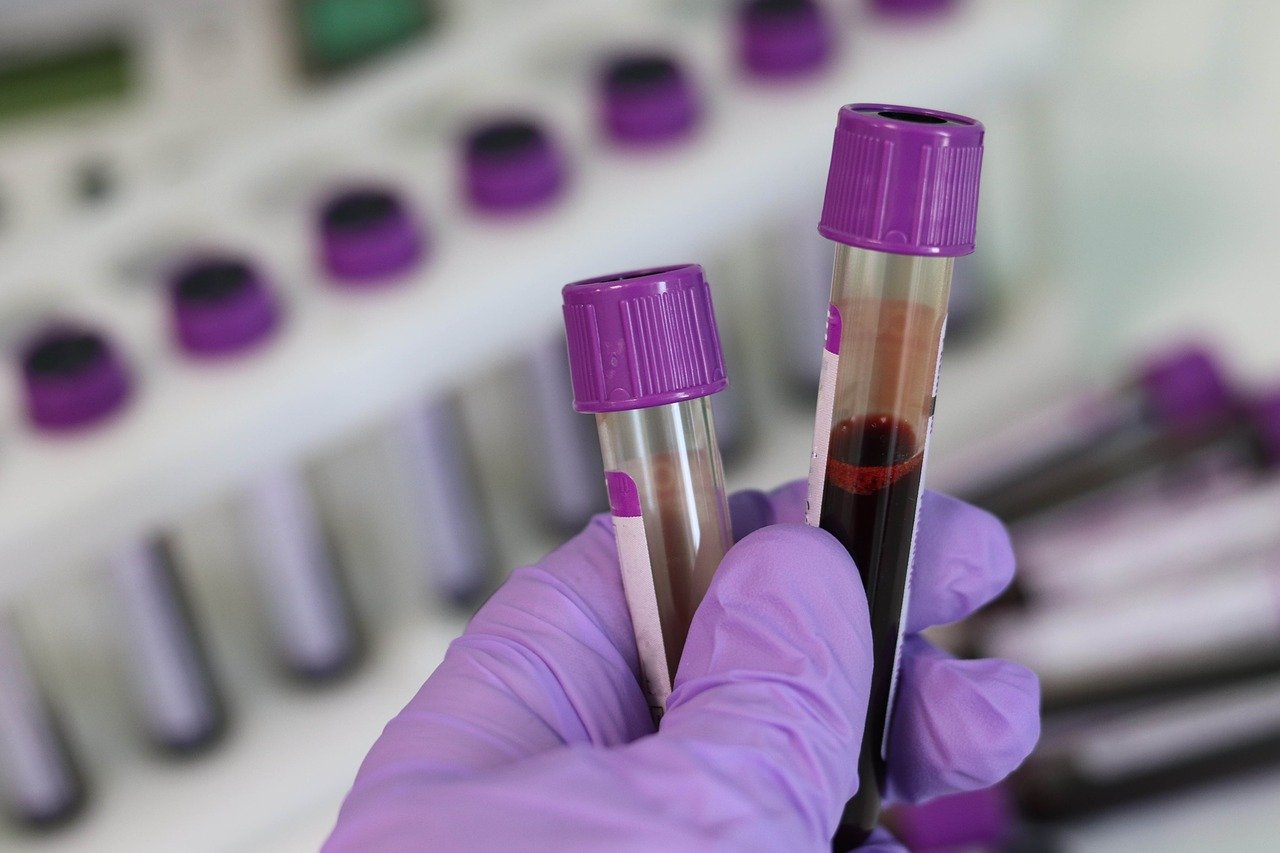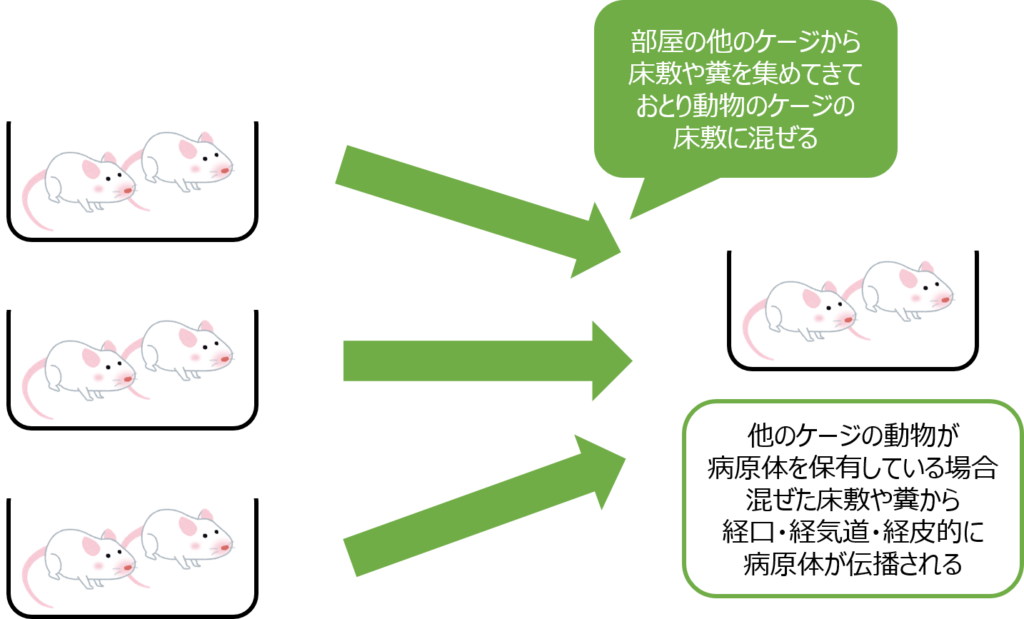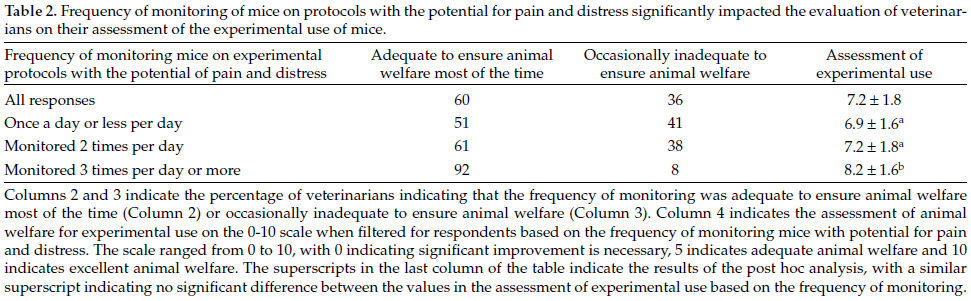がんも遺伝する:モード・スライの功績
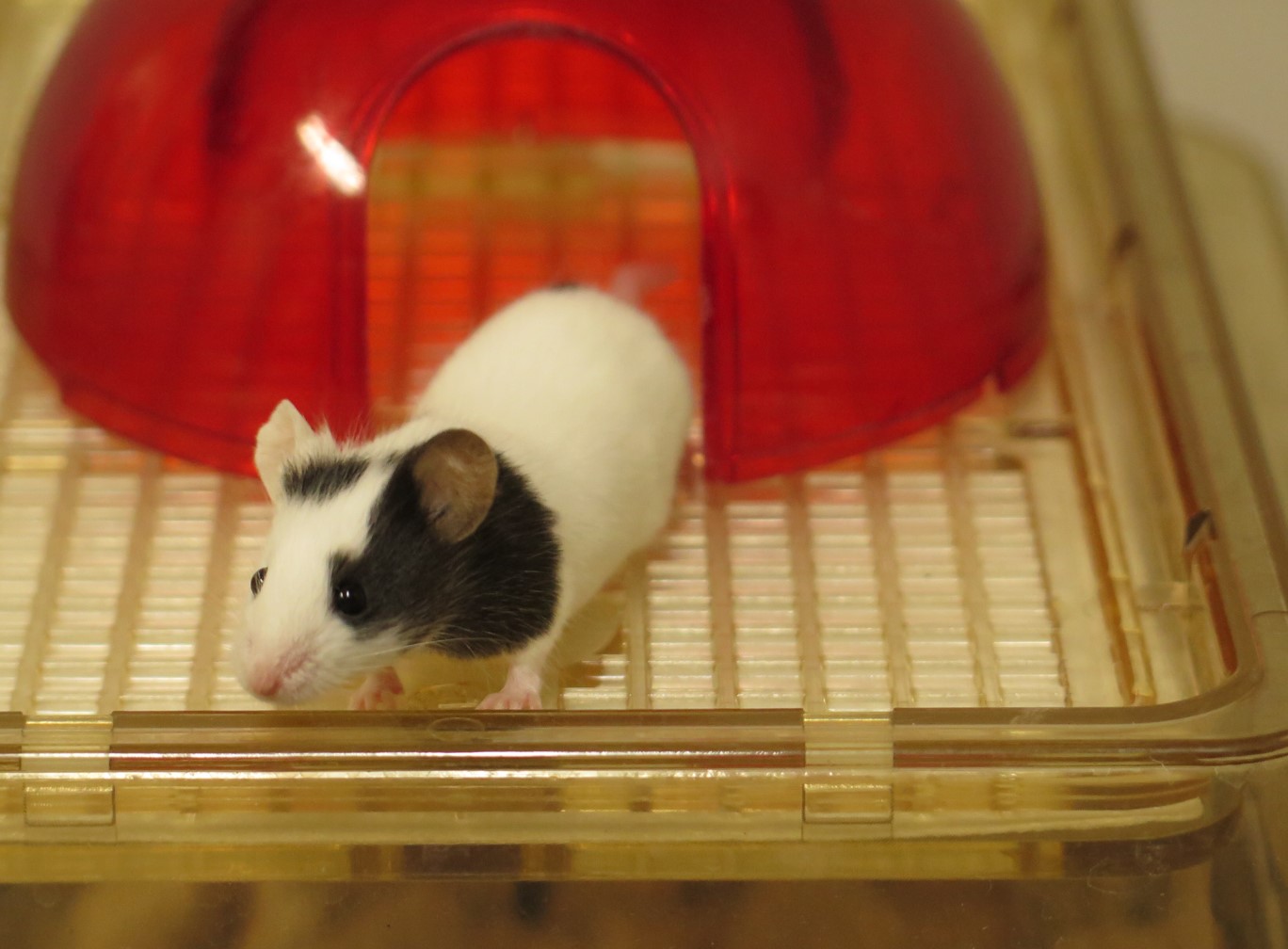
モード・スライ [9, 10, 11, 12]
スライは、1869年、ミネソタ州ミネアポリスで生まれた。シカゴ大に入学後、裕福ではなかったこと、また、当時、女性向けの奨学金はほとんどなかったことから、学費と食費を稼ぐためのアルバイトと勉学の多忙な大学生活を送る。その結果、体調を崩し、シカゴ大学を中退する。1899年、編入したブラウン大学で学士号を取得した。その後、師範学校の心理学の教職につき、遺伝学や精神医学に触れることになる。1908年、教師の仕事を辞め、シカゴ大学の動物学教授のもとで助手を務めることになった。病気の遺伝に興味を持っていた彼女は、6匹のJWMを使って研究を始め、JWMが、がん好発系でもあったことから、旋回運動の遺伝様式ではなく、がんの遺伝様式を調べることにした。がんを発症するマウスと、がんにならないマウスを交配させ、その子孫がどうなるかを観察した。彼女は、シカゴ大学構内の家に、数多くのマウスと暮すことになる。1911年にシカゴ大学の正規職員になるまでは、自費でマウスや餌、床敷を購入し、1日18時間、一人で多くのマウスの世話と観察を行った。マウスのために食事をしないことも度々あった。晩年の講演で述べているが、ケージを滅菌するなど衛生状態に非常に気を使っていたため、常時、数千匹のマウスを収容する実験室では、30年間、感染症の発生は無かった。飼育の状態や食事などの環境因子を極力同一にし、表現型のばらつきが生じないようにした。すべてのマウスの背後には、彼女が書き続けた100世代以上の先祖からの遺伝記録、臨床記録、剖検記録、組織学的記録が存在する。そのため、すべてのマウスの背景情報がわかり、どんな病気にかかりやすいか、何歳まで生きるか、どのような原因で死ぬかも予想できたようだ。彼女は、30年以上の研究生活で15万匹のマウスを交配・飼育して、マウスの表現型を詳細に観察し、そのうち3万匹に様々ながんが発生したことを記録している。1914年までに、5000匹にも及ぶ質量共に膨大な遺伝実験と剖検によって遺伝性腫瘍の存在を確認し、さらにがん抵抗性は優性形質、がん感受性は劣性形質であるとの説や、がん発生には特定の部位に継続的な刺激が必要であると提唱した。この結果をアメリカ癌学会や論文で発表し、脚光を浴びることになる。彼女の説は、上述のリトルから、がんにおける遺伝が果たす役割を単純化しすぎており、実際に起こっていることは、単一遺伝子のメンデル遺伝で説明されることよりも複雑であるという批判を受けた。しかし、筆者は、彼女の説は、今では当たり前となった遺伝性がんの概念を初めて発見したという点で極めて重要だったと思う。その後、彼女は研究を進めるうちに、がんの発生は遺伝の関与だけでは説明できないことを認識するようになる。後年、彼女は、がんの発生には、「遺伝的な感受性」と「がんになりやすい組織への長期的な刺激」という2つの条件が必要であると考えた。現在、遺伝性がんは、がん全体の10%程度であり、環境要因がどのように遺伝子を変化させ最終的にがんを引き起こすか、という研究が盛んに行われている。スライの研究はその端緒となった。1922年には助教授に、1926年に准教授に昇進した。1936年、欧州で開催された国際がん対策会議に出席のために、彼女はマウスを助手に任せ、26年ぶりに休暇を取った。それ以前には、カリフォルニアで病気療養中の母親を訪ねる際には、トレーラーを借りてマウス達を連れて行った。彼女は、1914年に米国医学協会から、1922年に米国放射線学会から金メダルを授与された。1923年にノーベル賞の候補にもなったが、受賞には至らなかった。また、1915年にシカゴ大学からリケッツ賞を、1937年にブラウン大学から名誉博士号を授与された。1944年にシカゴ大学を定年退職した後、余生をデータ解析に費やし、1954年に心臓発作で亡くなった。
関連記事

ARRIVEガイドライン2.0が公開されました
7月14日にNC3Rs(英国3Rセンター)にてARRIVEガイドライン2.0が公開(https://arriveguidelines.org/)されました。2010年に初めて公開されたARRIVEガイドラインは、動物実験計画において最低限記載すべき項目をまとめたものであり、Natureをはじめ多くの学術雑誌に支持されているガイドラインです。
そもそもこのガイドラインが作成された背景には、動物実験の再現性があまりにも低い(一説には70%以上の実験が再現できない)と言われてきたことがあります。その一因として実験方法の詳細が述べられていないとの指摘がありました。
英国の機関が、動物実験の記載がある271報(1999-2005)の論文を精査したところ、研究の仮説・目的を記載し、かつ動物の数と特徴が記載されていたのは271報のうち、わずか59%であったことを報告(https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0007824)しています。
これらの事を受けてNC3Rsは記載すべき20の項目を定めて2010年にARRIVEガイドラインとして発表しました。多くの研究機関や出版社から支持されてきたものの、記載項目が多いことからも問題の根本的な解決には至りませんでした。そこで改訂版であるARRIVEガイドライン2.0が新たに公開されました。
ARRIVEガイドライン2.0の主な変更点は以下のとおりです。
記載すべき最低限の項目を10項目に絞った「ARRIVE Essential 10」とそれらを補完する「Recommended Set」に分類した
ARRIVE Essential 10は以下のとおりです。なお正式な日本語訳は日本実験動物学会等、公的機関によるアナウンスをお待ちください。
1. Study design(研究計画)
2. Sample size(サンプルサイズ)
3. Inclusion and exclusion criteria(包含基準と除外基準)
4. Randomisation(ランダム化)
5. Blinding(盲検化)
6. Outcome measures(実験の帰結)
7. Statistical methods(統計学的方法)
8. Experimental animals(実験動物の情報)
9. Experimental procedures(実験処置)
10. Results(結果)
前回のガイドラインが20項目であったことからも項目数を絞って記載しやすくなっていることが分かります。通常の動物実験審査においては3~5の項目を審査することは少ないのですが、今後はこのあたりも審査することが求められてくるかもしれません。

 北里大学獣医学部 佐々木宣哉(JALAM教育委員会)
北里大学獣医学部 佐々木宣哉(JALAM教育委員会)