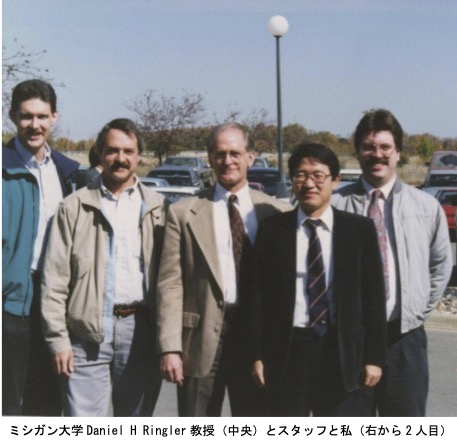遺伝子改変モデル動物の現在と展望

今後の展望: 獣医学分野への展開
私たちは現在、獣医学研究分野の部局に所属し、獣医学ならではの動物種を対象とした疾患研究にも遺伝子改変モデル動物を活かしたいと考えています。ヒト疾患モデルに比べると、獣医学分野で扱う動物種における疾患モデルはまだまだ多くありません。ある特定の動物品種で頻発するような遺伝病についても、多くの遺伝的多型の候補は挙がっているものの、因果関係を十分に検証できていないケースが多いのが現状です。その背景には、マウスほど飼育や繁殖が容易ではない動物が多く、個体数をそろえた研究が難しいという問題があります。そのため、マウスによる遺伝子改変モデル動物の作製がより簡便となった今、ヒト疾患のみならず、獣医学分野で取り扱われる動物の疾患にも積極的な貢献が期待されます。
このような疾患の中には、種差によりマウスでは再現できないものも存在します。ヒト疾患に関しては、特定の遺伝子をヒト由来のものに置き換えるなどの工夫がなされてきました。同じく、獣医学研究でも、利用される動物の特性に近づけたマウスの作製が期待されます。ただし、全ての遺伝情報をマウスから置き換えるのは困難です。そこで、私たちは「異種間キメラマウス」が新たな疾患モデルとして利用できるのではないかと着目しています。マウスの着床前の胚に異種由来の多能性幹細胞を加えることで、マウスの体の一部に異種由来の細胞が寄与したキメラ個体を作り出すことができます。異種由来細胞は全ての遺伝情報が対象の動物のもので構成されているため、対象の動物そのものを使わずして、マウスの飼育環境でその動物の遺伝子背景で個体レベルの分子遺伝学的な研究が行えると期待されます。実際に私たちは、ペットとして知られるアフリカチビネズミの細胞を用いてマウスとの異種間キメラ個体を作製できることを報告しました[文献7]。アフリカチビネズミはマウスほど繁殖力が高くなく、マウスのような個体レベルの研究が難しいとされています。キメラマウスでその特性を研究できれば、疾患や生理機能の理解が大きく進むと期待されます。
一方で、異種間キメラマウスに関する研究はいまだ黎明期にあり、多くの動物種ではマウスとのキメラ形成が難しいことが報告されています。また、異種間キメラマウスの作製には、対象とする動物に由来する多能性幹細胞が必要となりますが、多くの動物ではいまだ樹立方法が確立されていません。著者らは現在、さまざまな動物種に対して多能性幹細胞の樹立やキメラ作製の条件検討を行い、獣医学分野で課題となる疾患の再現や治療法の開発へとつなげたいと考えています。
以上のように、遺伝子改変モデル動物の作製技術はめざましく進歩しており、今後も基礎研究から応用研究、獣医学分野に至るまで、幅広い領域での活躍が見込まれます。新たな疾患モデルの開発のみならず、異種間キメラ技術による新たなアプローチにより、多様な動物種の生理・病態解析への展開やさらなるブレイクスルーが期待されます。
引用文献
1. Fujii W, Kawasaki K, Sugiura K, Naito K. Efficient generation of large-scale genome-modified mice using gRNA and CAS9 endonuclease. Nucleic Acids Res. 41(20): e187. 2013
2. Nakamura K, Fujii W, Tsuboi M, Tanihata J, Teramoto N, Takeuchi S, Naito K, Yamanouchi K, Nishihara M. Generation of muscular dystrophy model rats with a CRISPR/Cas system. Sci Rep. 4: 5635. 2014
3. Fujii W, Kakuta S, Yoshioka S, Kyuwa S, Sugiura K, Naito K. Zygote-mediated generation of genome-modified mice using Streptococcus thermophiles 1-derived CRISPR/Cas system. Biochem Biophys Res Commun. 477(3): 473-6. 2016
4. Fujii W, Ikeda A, Sugiura K, Naito K. Efficient generation of genome-modified mice using Campylobacter jejuni-derived CRISPR/Cas. Int J Mol Sci. 18(11). pii: E2286. 2017
5. Fujii W, Ito H, Kanke T, Ikeda A, Sugiura K, Naito K. Generation of genetically modified mice using SpCas9-NG engineered nuclease. Sci Rep. 9(1):12878. 2019
6. Ikeda A, Fujii W, Sugiura K, Naito K. High-fidelity endonuclease variant HypaCas9 facilitates accurate allele-specific gene modification in mouse zygotes. Communications Biology. 2: 371. 2019
7. Matsuya S, Fujino K, Imai H, Kusakabe KT, Fujii W, Kano K. Establishment of African pygmy mouse induced pluripotent stem cells using defined doxycycline inducible transcription factors. Sci Rep. 14. 3204. 2024

 東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 実験動物学研究室 藤井渉
東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 実験動物学研究室 藤井渉