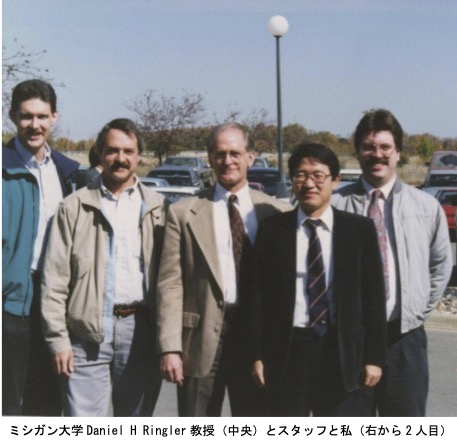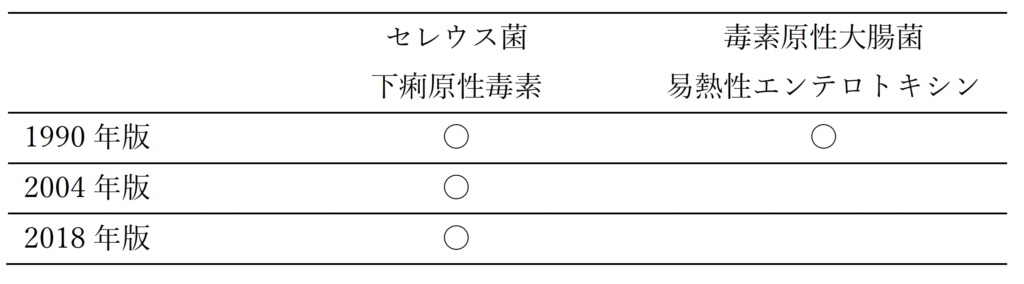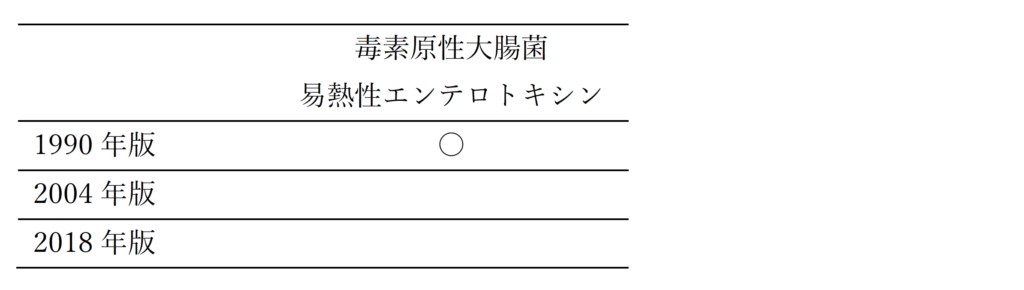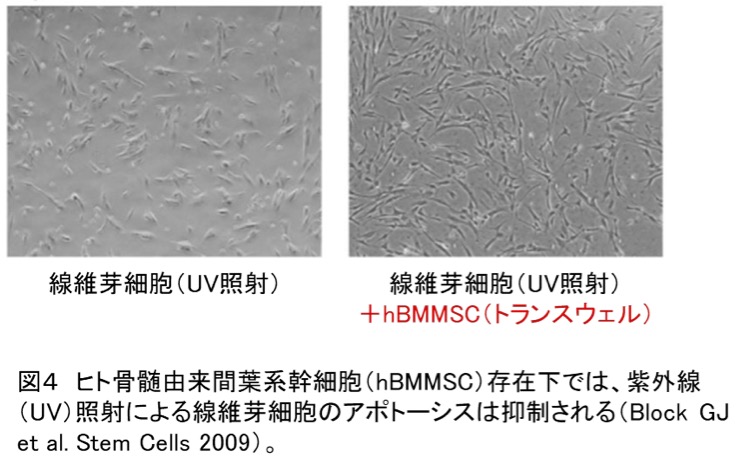- トップ
- コラム一覧

[学会情報]日本動物実験代替法学会第 36 回大会開催のご案内
日本実験動物医学会が後援している日本代替法学会が下記の日程で開催されます。JALAM会員は、代替法学会会員価格で大会に参加できますので、ぜひご参加下さい。
大会長 伊藤 晃成(千葉大学大学院薬学研究院)
開催日:2023 年 11 月 27 日(月)〜29 日(水)
会場:千葉大学 西千葉キャンパス(千葉市稲毛区弥生町 1-33)
テーマ: 動物実験代替法の終わりなき挑戦
ホームページ:https://jsaae36.secand.net/index.html
大会事務局:日本実験動物代替法学会第 36 回大会事務局
千葉大学大学院薬学研究院 生物薬剤学研究室
〒260-8675 千葉市中央区亥鼻 1-8-1
TEL: 043-226-2887、FAX: 043-226-2887
E-mail: jsaae36@gmail.com
運営事務局: 株式会社 JBE
〒140-0004 東京都品川区南品川三丁目6番地51号 NK南品川301
TEL: 03-6718-4952、FAX: 03-6718-4952
E-mail: jsaae36@jbe.co.j
コラム

第31回サル疾病ワークショップ参加者募集中
– – – – – – – – – – – – –
第31回サル疾病ワークショップ
– – – – – – – – – – – – –
マーモセットを用いた医学生命科学研究の現場から
【開催日】 2023年7月29日(土)
【開催形式】 ハイブリッド
• 会場 実験動物中央研究所 レクチャールーム
神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25-12
• オンライン zoom
■□ 第31回サル疾病ワークショップ参加者募集
締切: 2023/07/07
事前登録が必要です。
添付のプログラムをご参照の上,お申し込み下さい。
■□ 詳細,参加申込,発表申込,お問い合わせ
https://www.spdp.jp/2023/04/-2023/
【参加費用】
• 参加費 3,000円
• 昼食弁当代 1,000円 (希望者・現地会場のみ)
• 懇親会費 5,000円 (希望者・現地開催)
※事前のお支払いが必要です
【大会長】井上 貴史 (実験動物中央研究所)
コラム

動物福祉の評価ツールのご紹介-3 福祉を評価するツールを紹介するサイト2: NC3Rsの Welfare Assessment
2.実際上の侵襲性(物理的および心理的傷害)の評価と報告
ここでは、NC3Rsを設けている英国のガイダンス“Guidance to the Operation of the Animals (Scientific Procedures)Act 1986”2)に基づいて重症度の分類や分類時の注意点について説明されています。
●「適切な資格を有する者」は、各処置の実際の重症度を「回復しない」、「軽度」、「中度」、「重度」に分類しなければならない。
●この分類の根拠は、将来的な重症度や処置の種類ではなく、日々の(ケージサイドでの)福祉評価を総括したものなので、その場で目にする重症度とは違うかもしれないし、その後の状況によっては重症度も変わっているかもしれない。
これはつまり、「求められる知識やスキルを保持している人が重症度をしっかりと判定しなさい。加えて、重症度はさまざま条件で変化するので、通り一遍にならないようよく見なさい」ということだろうと思います。
なお、より詳しいガイダンスは、“European Commission severity assessment document and examples”に格納されている” European Commission (2012) Working document on a severity assessment framework“と”European Commission (2013) Examples to illustrate the process of severity classification, day-to-day assessment and actual severity assessment “を見るようにとも記載されています。

動物福祉の評価ツールのご紹介-2
〜福祉を評価するツールを紹介するサイト1:USDAのNational Agricultural Library〜
“Literature on Welfare Assessment and Indicators” 動物福祉の評価と指標に関する文献へのリンク集
福祉評価と福祉指標に関する文献を検索できるよう、産業動物用にPubAg、そして実験動物用にPubMedへのリンクが検索式とともに配置されています。検索式や検索文字列作成の詳細についても触れていて、丁寧です。
“Grimace Scale”
Grimace Scaleは「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準の解説」(平成29年10月)に記載があり、実験動物種ではいまや標準的な福祉指標になっていますが、典型的な実験動物種以外の動物について詳しく調べようとすると案外骨が折れるので、このページを知っていると便利です。Grimace Scaleは、顔の様々な部位や体の姿勢を評価することで、動物の痛みを評価するために用いられるスコアリングシステムです。このパートでは典型的な実験動物種や家畜以外の情報にもリンクが貼られています。
“その他の Web リソース”
最後のパートでは、マカクや動物園動物の福祉アセスメントにも対応できるようリンクが貼られています。
今回はこのくらいにして、次回は、英国NC3Rsの“Welfare Assessment”を扱いたいと思います。
なお、米国USDAの”Animal Welfare Assessments“を閲覧される際には、ぜひ一度は、National Agricultural LibraryのトップサイトのTopicsメニューを開いて”Animal Health and Welfare”のページにも寄ってみて下さい。いろいろな情報があることにお気づきになることと思います。